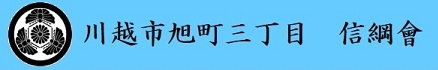信綱會では信綱さんから始まる大河内松平家(現在は大河内家)との関係を大切にしておりますんで、現在のご当主とも関わりを持たせていただいております。
そこで、信綱さんの子孫たちをご紹介していこうと、こうしてやって来たという次第でございます。
まぁ、信綱さんは「知恵伊豆」なんて申しまして少しは名が通っております。ですが、子孫の皆さんはどうも世に知られていない。
「大した人がいなかったから」なんてお思いになりますでしょ。いやいや、優秀な方や、歴史上重要な方、なかなか魅力的な謎を持っている方と実はお話ししたい方がたくさんおるんです。
そもそも信綱さんから始まる「大河内松平家」というのは、幕府にとってとても重要な家柄でございました。
江戸時代、老中を拝命したものは、再任など重複するものを除く人数で言いますと150人ほど。家柄ですと75家となります。そのうち半数の家柄が老中を1人しか輩出しておりません。
最も多く老中を輩出したのが雅楽頭系酒井家で7名。
次が阿部家宗家、忠秋系阿部家、大給松平家で6名ずつ。
その次が正成系稲葉家の5名。
大河内松平家(吉田藩系)は、大久保家宗家、関宿系久世家、忠元系水野家と並び4名と多くの老中を輩出している家柄なんでございます。
論評の多くが、「信綱さんが偉大だったから子孫も多く重役に取り立てられた」というようにいっているんですが、そう単純なものでもなさそうなんですな。
他の家系は代々幕府の職務を任され続けているんです。だからこそ目にかけられて老中に任命されるわけです。
ところが、大河内松平家は様子が違いましてね。
信綱さんの息子は、後を継ぎますと幕府の仕事はしておりません。それなのにその孫(信綱さんからするとひ孫)は老中となりまして、その後も老中を多く輩出しているんですから不思議じゃぁございませんか。
どうです、興味がわいてきましたか。
ではそろそろ本題とまいりましょう。
・●◆●・
川越氷川祭禮を見物した松平輝綱さん
輝綱さんは、父親の信綱さんが川越藩主になりますと頻繁に川越に訪れておりますし、今の川越まつりにつながる川越氷川祭禮を見学しております。藩主を継ぎましてからはずっと川越藩でございましたから、実は信綱さんより馴染み深い存在のはずなんでございます。
でも、あんまり知られていない。もったいないですな。
そんな輝綱さん、元和元年といいますから1620年、信綱さんの長男として生まれました。この時信綱さん26歳。当時としましてはいい年齢でございますんで、やっと産まれてくれたかといった感じでしょうか。
ただ、信綱さんが小姓組番頭になったのが28歳の時でございまして、その時でも八百石。地位としてはまだまだといったことろでございます。
輝綱さんが14歳の時、将軍上洛に際して供となった父信綱(39歳)に同行しておりまして、翌年には従五位下甲斐守となっております。信綱さんはこの前年、寛永10(1633年)年に老中になっております。
島原の乱では上使として出陣した父信綱に従いました。この時、輝綱17歳でございます。
この島原の乱では、2カ月に及ぶ兵糧攻めの後にやっと城攻めが決まりますと、輝綱さんは単騎城を目指して馬を走らせました。武功を上げようというんですな。
この時、「論功行賞のために参陣している諸藩にこそ功をあげさせなければいけない」と、家臣が死に物狂いで止め、引き返させたという話が残っております。
この時、止めに入った家臣を一度は切ろうとしたといいますから、若者らしい、血気盛んな様がうかがえますな。
信綱さんは、この島原平定の功で川越藩主となりました。
その後、忙しい父、信綱さんに代わりまして幕府の仕事をこなしたり、川越を訪れて信綱さんの発案である町割りや新河岸川、川越街道の整備、新田開発などを成功させております。
その他、江戸と川越の里程を実測するという事業も行っておりますが、この辺りは信綱さんの子だなぁと感じられます。
川越祭りは、江戸の天下祭りを参考に上覧祭りとして発展しておりますが、信綱さんは忙しもんですから、ほとんど川越には来ておりません。冒頭でも触れましたが、輝綱さんがこの役をかっていたようでございます。
慶安5(1652)年、浪人たちが幕府転覆を狙った承応事件の際に信綱さんのところに密告があったんですが、これを受けまして川越氷川祭禮を見物していた輝綱さんを急遽呼び戻した、という記録がございます。
この川越氷川祭禮が上覧祭りとして発展し、川越まつりになっていくわけでございますね。川越まつりのことにつきましては解説がいろいろございますんで、そちらをご覧ください。
社交面でも様々な記録が残っておりまして、信綱さんの嫡男として、次代を担うものと周囲からも認識されておったようでございます。
このように信綱さんが健在な間は精力的に幕府の仕事に励んでいた輝綱さんですが、信綱さんが亡くなり川越藩主を継ぎますと、病弱を理由に幕政に関わることを辞退する旨、願い出まして、これが承認されております。この時、輝綱さん43歳でございます。
そんなに病弱だとは思えないんですがね。
輝綱さんに関する記録を見ていますと、慶安元(1648)年に吹き出物治療で、承応2(1653)年に肩を痛めたため、承応3(1654)年には理由不明で、いずれも相州塔沢温泉に行っておることが分かります。
この塔沢温泉といいますのは箱根でございますんで、結構な遠出でございます。特に承応2年と承応3年は江戸からではなく川越から向かったといいますから、そんなに重症だとは思えません。
また不思議なことに、信綱さんの死後、岩槻にあった菩提寺の平林寺を遺言に従って野火止(新座)に移転させたという記録以降、まったくといっていいほど輝綱さんの記録は残ておりません。
ごくわずかに残っておりますのは次のようなものでございます。
「知惠伊豆即ち松平信綱の嫡子甲斐守輝綱は火器を専門に研究した人である。鎧を造ってそれを鉄砲で撃って貫通の程度を試験した。其鎧が残って居りますが、さうした研究に生涯を暮されました。その人は天文にも通じた人で、西洋人の書いたものを写したりして居る。又鉄砲を撃って幾ら当たると云ふプロバビリティ(確率)の萌芽ともなるべき小著もある。」
これは三神義夫が書いた「我が国文化史上より見たる珠算」にあるのですが、何に依って書かれたものかは不明です。
この他「兵法や薬学の研究をした」「日本で初の経度と緯度を入れた地図を工夫した」とも言われておりまして、まぁ噂のようなものではございますが活動的な印象ですよねぇ。
こんな状態なのに幕府の役務を辞したというのも、それを幕府がすんなり認めたというのも不思議でなりません。何か裏があるんでしょうか。
輝綱さんは、漢文11(1670)年に51歳で亡くなりました。藩主を継いで8年のことでございます。
川越藩を去った松平信輝さん
松平輝綱さんの跡を継ぎましたのは、輝綱さんの四男である松平信輝さんでございます。初名は晴綱でしたが、19歳で結婚し、その翌年に改名しております。祖父の信綱さんから「信」、父の輝綱さんから「輝」をもらった形ですんで、ご本人かなりの決意だったんでしょうか。
信輝さんは先ほども申しました通り四男なんですが、お兄さんたちが早くに亡くなってしまいましたんで嫡男となりました。跡を継いだのが13歳と言いますから早かったんですな。
信輝さん、跡を継いだのが若いというだけでも大変だったでしょうに、生まれながらに聞こえに難があったようでございまして、嫡男の信祝さんが育ちますとしばしば名代を務めさせたといわれております。
このようなわけですんで信輝さんが川越藩主を継いだ際には、「能力はあるが耳が遠いのであればいかんともしがたい」ですとか、「祖父の威光のみではどうにもならないだろうから、近々川越から移されるだろう」だなんて噂されておったようです。
史料で言いますと、『土芥寇讎記(どかいこうしゅうき)』という江戸中期の各藩や藩主の評を記した書物には「たとい祖父信綱の忠勤を上に思(おぼし)食(め)さるると雖(いえど)も、当伊豆守(信輝さんのこと)その器に非ずんば、いかが御膝下の城に差し置かせらるべきや」と厳しい言葉が記されております。
この『土芥寇讎記』が世に出た4年後、元禄7(1694)年に大河内松平家は下総の古河に転封されました。信輝さんは34歳、息子の信祝さんは11歳の時でございますので、信輝さんが川越藩主だったのは22年間ということになります。ですから、跡を継いですぐに国替えをさせられたというわけではございません。
ともかく『土芥寇讎記』に記されている通りになったわけでございますが、じゃぁ古河ってところは、川越よりもひどい格下かと申しますとそんなことはございません。
古河藩は関八州の中央部にあたりまして、渡良瀬川、利根川水系を望む水上交通の基幹となっておりますし、奥州街道(日光街道)の宿場町でもあります。
川越夜戦(川越合戦)で川越を攻めた足利公方は古河公方とも呼ばれておりますが、古河を拠点としておりました。
大河内松平家が古河に入る前には、大老の土井利勝や同じく大老の堀田正俊も治めていたことがあるんですから、川越から古河に移ったことで大河内松平家が幕府から軽視されたということにはなりません。
最近の発見になりますが、2020年に豊橋の民家から「戸田忠昌という人から信輝さんに宛てた書簡」が見つかっております。内容は、「公方様(将軍)の機嫌がよかったので、他の老中と相談のうえ、信輝が献上した甜瓜(まくわうり)一箱を披露した」というものでございます。
書簡には日付は書かれておりますが、年が書かれておりませんので、いつのものかははっきりしませんが、「他の老中と」とありますんで、戸田忠昌が老中だった時期、天和元(1681)年から元禄12(1694)年の間ということになります。この時期は信輝さんが川越藩主だった時代でして、川越は甜瓜の名産地だったそうでございます。
ここからは、信輝さんは全く幕府と関わっていなかったというわけではなく、挨拶など関わりを保っていたということが分かります。
また、川越には信輝さんが修理させたという建物がございます。伊佐沼にある薬師神社本殿がそれで、修理されたのは元禄5(1692)年のこととされています。また、同じ年に川越城内に八幡社を建立したという史料もございます。
信輝さんは古河藩に移りますと、城内に頼政神社を見つけました。この頼政神社の祭神は源三位頼政なのですが、この頼政は大河内家の遠祖にあたります。
信輝は大変喜んだそうで、さっそく社殿を修築しております。またこのことを弟で高崎藩主である松平輝貞さんにも知らせたのでしょう。輝貞さんは高崎城内に頼政神社を勧請しております。
信輝さんは50歳まで藩主として務め、病身を理由に隠居して「宋見」と名乗り、跡を信祝さんに託しました。この時、信祝さん27歳でございます。
隠居したんだから大人しくしていたかと言いますとそうではなかったようでして、宋見さん直属の家来たちを持ち、藩政にもたっぷりと口を出しておったようです。
後に宋見さんが危篤となった時のこと、先ほどちらりと出てきました宋見さんの弟、松平輝貞さんに対し、信祝さんがこんな言葉を送ったそうでございます。
「これまでも幕府に関することや、家中の仕置きなど様々なことについて相談したいと考えていたが、隠居宗見から指示を得ていたので行き違いになっては迷惑だろうと遠慮していた」「今後は判断に迷うようなことがあったら相談させていただきたい」
口うるさいおやじの姿が想像できます。
こんなこともございました。宋見さんが隠居し、信祝さんが古河藩主となった2年後の正徳2(1712)年、大河内松平家に三河吉田への転封の命が下ったのです。
これに先立ち、信祝さんに江戸城に参るようにとの老中からの奉書が江戸屋敷に届いたのですが、この時、信祝さんは古河におりました。
さっそく古河まで馬を急がせて、となるかと思いきや、留守居役は宋見さんに奉書を渡しまして指示を仰いでおります。この時点でも藩政に大きな影響力をもっていたことが分かります。
こんな様子からは、耳の聞こえが悪いから政務がまともに執れないだろうなんて言われたようには思えませんし、隠居するほど病身の身とも思われません。
信輝さんは、享保10(1725)年6月18日に66歳で亡くなりました。